中国料理に欠かせない調味料といえば、「醤(ジャン)」。日本の食卓でも豆板醤や甜麺醤などが広く親しまれています。一方で、「使い方が難しそう」「レパートリーが限られる」といった声も。
そこで、今回は中華醤のエキスパートである、東京・浅草にある「四川料理 巴蜀(はしょく)」のオーナーシェフ・荻野亮平さんをお招きし、中華醤の魅力を深掘り! 味の素社食品研究所でさまざまな中華醤の開発を手がける、金森さんと長谷さんを交えた中華醤にまつわるトークをお届けします。

インタビューした人
「四川料理 巴蜀」代表
荻野亮平さん
1978年大阪府出身。辻調理師専門学校卒業後、1999年より東京・千駄木の「天外天」で四川料理を学ぶ。その後、中国・四川への留学を経て、2007年に福岡で独立・開業。2023年に現在の浅草の地に移転。2024年に信州大学の修士課程に入学し、自店の営業と並行して大学に通いながら、発酵唐辛子の研究に勤しむ。共著に『伝統×現代 深化する中国料理』(旭屋出版)がある。

インタビューした人
食品研究所 メニュー調味料グループ
長谷縁さん
「CookDo®」中華シリーズのレシピ作りを担当。中華醤の魅力に取りつかれ、中国のありとあらゆる中華醤を買い集めては食べ比べ、おいしい使い方や楽しみ方を研究中。「いろんな方に自分好みの調理を楽しんでもらえたらと思います。その中に醤があればなお幸せです」

インタビューした人
食品研究所 ソースグループ
金森有香さん
主に家庭用中華醤の開発・研究を担当。中華醤の家庭料理での楽しみ方を広げるべく、お客さまの声に耳を傾け、商品のブラッシュアップや発信に役立てている。
- 紀元前生まれ!うま味・香り・コクを深める調味料「醤」
- 入れるタイミングで味が変わる!醤使いのコツとは?
- 中華醤を使っていつもの料理を自分好みにアップデート!
01
紀元前生まれ!うま味・香り・コクを深める調味料「醤」
中国料理の「醤(ジャン)」の歴史は古く、紀元前の記録にもその名が見られるほど、中国の食文化に根付き、発展してきた調味料。中国では地域ごとに、発酵しているものから非発酵のものまでさまざまな種類があり、現在では主にペースト状の調味料を総称して「醤」と呼ばれています。

荻野さん「中華醤には、いわゆるしょうゆや塩などの日本の一般的な調味料では補えない、独特のうま味と香りがあります。四川料理は、宮廷料理を起源とする上海料理や広東料理に比べると、より家庭料理に近い味わいで、いかにご飯と一緒においしく食べられるかというのを大事にしています。そういう点でも四川料理に中華醤は欠かせない調味料ですね」
荻野さんは古い文献などを参考に、研究も兼ねて自店で使う中華醤の一部を手作りしています。その数は15種類以上あるのだとか!

荻野さん「辛味が欲しい時はこれ、うま味を足すならこれと、作る料理によって使い分けています。中国料理はある程度“この料理にはこの調味料”というのが決まっていて、僕の場合、独自の配合で個性を出すというより、中国で培われてきたルーツや作り方・使い方を大事にしています」
column 《醤のマメ知識》
【豆板醤】 そら豆、唐辛子を原料とした四川を代表する発酵調味料。中国では地域ごとに発酵やカビ付けの方法が異なるが、基本的な作り方は、割れたそら豆に麹(=各地域に根付いた菌やカビ)を付着させてそら豆麹を作り、刻んだ唐辛子と共に塩水に浸けて熟成発酵させる。1660〜1722年頃、福建省から四川省に移動してきた漢民族が持ち歩いていた乾燥そら豆が偶然雨に濡れてカビが生え、それが豆板醤のルーツと言われている。
【甜麺醤】 小麦粉を原料とした中国北部発祥の発酵調味料。小麦粉を練って蒸し、それを細かくして麹を付け、塩水を混ぜ、半年から1年ほど発酵させて作る。四川省では1853年に成都市に味噌工場のようなものができたことで広まったと言われている。四川料理では、回鍋肉、豚肉の細切り炒め、干し肉の甜麺醤風味に使うのが一般的。
02
入れるタイミングで味が変わる!醤使いのコツとは?
当日は、味の素社の食品研究所で荻野シェフを招いた中華醤の勉強会も行われました。中華醤の歴史を知る講義に始まり、後半には「Cook Do®」シリーズの中華醤、「熟成 豆板醤」と「甜麺醤」を使った料理も披露してくれました。

調理後、実際に味の素社の中華醤を使ってみて、食べてみての感想を荻野さんに聞いてみました。
荻野さん「自家製醤と比べた感想になってしまいますが、『熟成 豆板醤』はしっかり辛みがあるなと。『甜麺醤』は豆豉(とうち)が入っているのが珍しいですね。粘度が程よく、チューブ状のものは調理中に辛味を加減しながら足したい時に便利ですね」

金森さん「ありがとうございます。『熟成 豆板醤』は、辛味の強い辣醤(ラージャン)と、熟成発酵させた豆板醤のブレンドにこだわっています。今おっしゃってくださったように、少量でもインパクトのある辛さが味わえます。定番の麻婆豆腐や野菜炒めはもちろん、卓上で焼き鳥や餃子にちょい足しするのもおすすめです」
金森さん「『甜麺醤』は、良質な赤味噌をベースにそら豆みそをブレンドし、豆豉とごま油の風味が引き立つバランスに仕上げています」

長谷さん「先ほどの調理実習では、『熟成 豆板醤』を入れるタイミングを変えた2つの麻婆豆腐を作っていただきました。あらためて、その意図を教えていただけますか?」

荻野さん「結論から言うと、先にねぎを炒め、後から豆板醤を入れるのが普段私が行っている作り方です。中国料理はメイラード反応(※)による香りが魅力の一つなので、料理全体の香りを引き立たせることが重要。まず薬味を油で炒めて食材にまとわせてから、最後に中華醤を加えて風味を引き立たせることで、薬味と醤、両方の香りを両立することができます」
※食材に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで、香ばしい風味が生まれる化学反応。

金森さん「なるほど! 他にも使い方のコツがあれば教えてください。中華醤に合う食材などはありますか?」
荻野さん「中華醤は意外とどんな食材にも合います。個人的には、水分の少ない料理に使った方が、香りが引き立っておいしいと思います。同じ材料でも、中華醤を入れるタイミングによっても変わってきます。先ほどのように香りを引き立たせてから使うことで、麻婆豆腐や回鍋肉など家庭の定番料理がぐっとおいしくなるはずです」

03
中華醤を使っていつもの料理を自分好みにアップデート!
中華醤トークの最後に、お三方それぞれが感じる中華醤の魅力を語っていただきました。
荻野さん「僕は、普段から口の中に残る味の滞在時間を考えて料理をしているのですが、中華醤は味わいに余韻があるので、ご飯に合うおかずと相性がいいと思います。中華醤はうま味やこく、香りを増強してくれる有効な調味料なので、気負わず、なじみのある中華メニューに取り入れてみてください。きっと奥行きのあるおいしさを感じられるはずです」

金森さん「これまで中華醤の歴史や地域性を体系的に知る機会がなかったので、荻野シェフのお話がとても勉強になりました。その上で、やっぱり中華醤の魅力は、まだまだ知らない味わいがあり、自分好みの味を追求できるところだなと再確認。いつもの料理にちょい足しするだけで本格的な味わいに近づけるし、使う量や他の調味料との組み合わせ方で、さらに料理の幅を広げられる。その楽しみをお客さまにも伝えていけたらと思います」
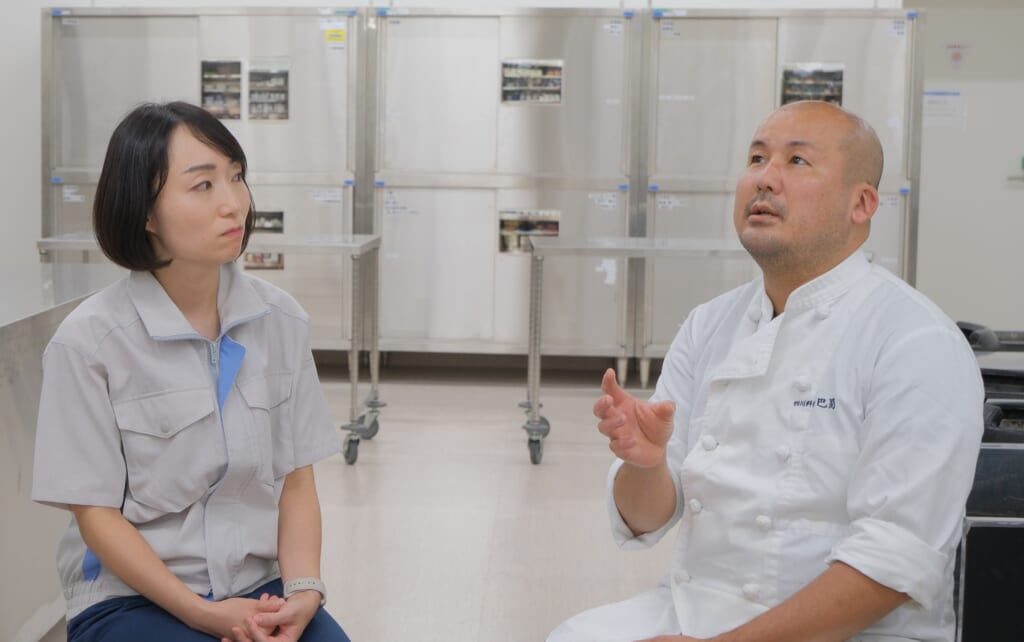
長谷さん「日本の調味料で辛味を出そうとすると、一味唐辛子や七味唐辛子、鷹の爪などの乾燥したものを使うことが多いと思うのですが、フレッシュな唐辛子から作る豆板醤のような中華醤は新たな辛味とおいしさを感じてもらえる調味料だと思います。日本人が好む味噌のような発酵の風味があるので、意外とどんな料理にも使っていただけると思います。 今回、荻野シェフにご協力いただいた勉強会を通して、日本のお客さまが好む味を長年研究し、作り続けてきた味の素社ならではの中華醤のおいしさや特徴があることも再認識できたので、今後さらにより良いアップデートを目指したいと思っています!」
荻野シェフの特製レシピはこちら
麻婆豆腐
材料
- 豚ひき肉
- 40g
- 絹ごし豆腐
- 400g
- 長ねぎ(白い部分)
- 1/2本
- 「Cook Do®」熟成豆板醤
- 大さじ1と1/2
- 「Cook Do®」甜麺醤
- 小さじ1
- A 水
- 1/2カップ
- A うま味調味料「味の素®」、A 粉山椒
- 各少々
- ごま油
- 大さじ1
- 水溶きかたくり粉
- 適量
調理手順
- ねぎはみじん切りにする。豆腐は2㎝角に切る。
- フライパンにごま油を熱し、豚ひき肉を炒める。
- 豚肉に焼き色がついたら、ねぎを加えてさっと炒め、「Cook Do®」熟成豆板醤、「Cook Do®」甜麺醤を加えてさらに炒める。
- Aを加え、ひと煮立ちしたら豆腐を加える。さらに5分ほど煮込み、水溶き片栗粉でとろみをつける。
醤爆茄子(ジャンバオチェズ)
材料
- なす
- 2本
- 長ねぎ(白い部分)
- 1/3本
- しょうが
- 1かけ
- ごま油
- 大さじ1と1/2+大さじ1
- しょうゆ
- 大さじ1
- 「Cook Do®」甜麺醤
- 小さじ1
- 砂糖
- 小さじ1
- 水
- 50ml
調理手順
- なすのヘタを除いて半分に切り、1.5cm幅の棒状に切る。ねぎとしょうがはみじん切りにする。
- フライパンにごま油大さじ1と1/2を熱してなすを加えてふたをして加熱する。焼き目がつき、しっかり火が通ったら、一度取り出しておく。
- 同じフライパンにごま油大さじ1を加え、ねぎとしょうがを炒める。香りが出たら、しょうゆ、「Cook Do®」甜麺醤を加えて軽く炒め、分量の水を加えてひと煮立ちさせる。砂糖を加え、なすを戻し入れ、中火で汁気がなくなるまで煮詰める。
知れば知るほど奥深い中華醤の世界。まずは気軽に使える「Cook Do®」シリーズの中華醤のちょい足しで、あなたも中華醤のある食卓を楽しんでみませんか?









